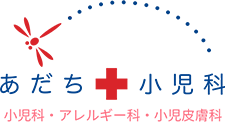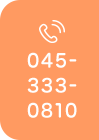溶連菌感染症
 溶連菌はのどが痛くなる感染症です。
溶連菌はのどが痛くなる感染症です。
一般的にお子さんが「のどが痛い」という時、その大部分はウイルスが原因で“のど”に炎症を起こしている状態です。細菌の原因は溶連菌による感染症が重要でこどもに多い疾患です。
溶連菌は、正式には溶血性連鎖球菌と呼ばれる細菌で、α溶血とβ溶血を呈する2種類があり、後者でヒトに病原性を有するものは、A群、B群、C群、G群などがあります。溶連菌感染症の90%以上がA群によるものです。したがって、一般的にはA群溶血性連鎖球菌(A群β溶血性連鎖球菌)による感染症を溶連菌感染症と呼びます。主に“のど”に感染して、咽頭炎や扁桃炎を呈し、それに全身に小さく紅い発疹を伴う場合があります。
劇症型溶連菌感染症
溶連菌感染症の中には劇症型溶連菌感染症というものがあります。稀な病気ですが、症状は発熱、手足の痛みから始まり、菌が全身に広がります。発症から多臓器不全に至るまでの経過が急激ですので注意が必要です。
溶連菌感染症の症状
症状の代表的なものは、発熱(38〜39℃)と“のど”の痛みです。しかし、3歳未満ではあまり熱があがらないこともあります。特徴的なのどのブツブツとした発赤や体や手足に小さくて紅いかゆみを伴う発疹が出たり、舌にイチゴのようなツブツブができたりします(イチゴ舌)。そのほかに頭痛、首すじのリンパ節の腫れ、腹痛や嘔吐などの腹部症状もみられます。急性期を過ぎると、発疹のあとに手足の落屑(皮むけ)が認められることもあります。風邪と違って咳や鼻水が少ないのもこの病気の特徴です。
学童期の方に多く感染し大人でもかかる場合があります
溶連菌感染症の感染経路
唾液などを介してうつる飛沫感染です。集団生活をする保育園、幼稚園、学校で感染する他家族内でも感染しやすくなります。
溶連菌感染症の検査と治療
症状などから溶連菌に感染している疑いがあれば、確認のための検査を行います。検査は喉の咽頭培養検査もしくは迅速キットで検査を行います。急性期の検査ではありませんが、血液検査で抗体の上昇を確認する方法もあります。溶連菌は健康でも保菌しているお子様もいるため、症状などから判断し検査の内容を決めていきます。
治療の基本は抗生剤です。また症状に合わせたお薬も処方いたします
治療開始後2〜3日で熱が下がり、のどの痛みもやわらいできます。発疹が出た場合、急性期を過ぎて、手足の指先から始まる落屑(皮むけ)が認められることがあります。確実に溶連菌を退治し、重大な続発症(合併症)を引き起こさないために、症状が消えても抗生剤は決められた日数を飲み切ってください。抗生剤の種類によって7~10日間内服します
溶連菌感染症の続発症(合併症)
溶連菌感染によって心臓弁膜に障害などを起こすリウマチ熱や、急性糸球体腎炎といった合併症を起こす場合があります。
そのため決められた日数の抗生剤をしっかり内服し治療してください
子どもだけじゃない?大人も注意
 溶連菌感染症といえば「子どもの病気」というイメージを持つ方も多いですが、実際には大人も感染することがある感染症です。特に、家庭内や保育園・学校などでお子さまが感染した場合、同居している大人への感染リスクは決して低くありません。
溶連菌感染症といえば「子どもの病気」というイメージを持つ方も多いですが、実際には大人も感染することがある感染症です。特に、家庭内や保育園・学校などでお子さまが感染した場合、同居している大人への感染リスクは決して低くありません。大人が感染すると症状が重くなることも
溶連菌は飛沫感染や接触感染によってうつるため、家族内での感染がしばしば見られます。大人が感染した場合、典型的な咽頭痛に加え、高熱や強い倦怠感、関節痛、頭痛など、子どもよりも全身症状が強く出る傾向があります。 また、「風邪のような症状」として捉えられがちで、インフルエンザ検査では陰性、コロナでもなく、「ただの風邪」と見過ごされてしまうケースも少なくありません。こうした場合、適切な抗菌薬治療が行われず、症状が長引いたり、合併症(急性腎炎、リウマチ熱など)につながる可能性もあるため注意が必要です。
感染拡大を防ぐために大人も検査を
「子どもが溶連菌にかかった後から、喉が痛くて高熱が続いている」「風邪薬が効かない」と感じたときは、早めに医療機関を受診し、溶連菌の有無を検査してもらいましょう。迅速検査により短時間で結果がわかり、早期治療につなげることが可能です。 また、適切な抗菌薬を服用することで、24時間以内には他人への感染リスクも大きく減少します。ご家族内に小さなお子さまや高齢者がいる場合は、十分な注意が必要です。
ご自宅でのホームケア
食事
 喉の痛みがあるので「熱い」、「辛い」、「すっぱい」といった“のど”に刺激の強いものは避けてください。なるべくのどごしがよく、消化のよい食べ物にしてあげてください。食べるのがつらいようでしたら水分だけでもしっかり摂るよう心がけてください。その場合も炭酸水といった“のど”に刺激を与える飲料水は避けてください。
喉の痛みがあるので「熱い」、「辛い」、「すっぱい」といった“のど”に刺激の強いものは避けてください。なるべくのどごしがよく、消化のよい食べ物にしてあげてください。食べるのがつらいようでしたら水分だけでもしっかり摂るよう心がけてください。その場合も炭酸水といった“のど”に刺激を与える飲料水は避けてください。たとえば、、のどごしがよいもの:ゼリー、プリン、ヨーグルト、スープ、茶碗むし
消化の良い物:パンがゆ、野菜の煮もの、うどん、そうめん、豆腐、白身魚など
入浴
熱が下がれば、お風呂に入っても特に問題はありません。
症状が改善しない時
お薬(抗菌薬)を飲み始めて2〜3日たっても熱が下がらず、“のど”の痛みも消えないようでしたら、再受診してください
登園や登校について
治療開始後24時間以上経過し全身状態が改善していれば登園登校は可能です
糸球体腎炎の早期発見と予防のために
糸球体腎炎は溶連菌感染症の合併症の1つで、溶連菌感染症にかかった2~4週間後に発症します。むくみが気になったり、突然、血尿やたんぱく尿が出たり、尿の回数が少なくなったります。尿の色がにごっていたり、コーラ色の尿が出たりした場合は血尿の可能性があります。また、たんぱく尿が出ている場合には尿が泡立ちます。溶連菌感染症にかかった場合は、尿の色や状態に気をつけ、変化を認めた場合はすぐに受診するようにしてください。
症状の変化をみれば尿検査は不要、といわれているクリニックも多くありますが、当院では実際、溶連菌感染症後糸球体腎炎の患者様の経験もあるため、より安心して経過を見るために治療後の尿検査をお願いしております。
よくある質問
溶連菌感染症は自然に治ることがありますか?
溶連菌感染症は、軽症の場合でも自然に症状が改善することがありますが、抗菌薬による治療が推奨されます。適切な治療を行わないと、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症を引き起こす可能性があるため、医師の診断のもと、指示に従って治療を進めることが重要です。
溶連菌感染症の潜伏期間はどれくらいですか?
溶連菌感染症の潜伏期間は、一般的に2〜5日程度とされています。感染者との接触後、数日以内に喉の痛みや発熱などの症状が現れることが多いため、感染の可能性がある場合は早めに医療機関を受診し、適切な対応を行うことが大切です。
溶連菌感染症は何度もかかることがありますか?
はい、溶連菌感染症は再感染することがあります。溶連菌には複数の型が存在し、一度感染しても他の型に対する免疫ができるわけではありません。そのため、過去に溶連菌感染症にかかったことがある場合でも、再度感染する可能性があります。
溶連菌感染症の診断にはどのような検査がありますか?
溶連菌感染症の診断には、通常迅速抗原検査や咽頭培養検査が用いられます。迅速抗原検査は短時間で結果が得られるため、診断と治療の開始が迅速に行えます。ただし、検査結果が陰性でも症状や流行状況を考慮して治療が行われることもあります。
溶連菌感染症にかかった場合、学校や保育園への登校・登園はいつから可能ですか?
溶連菌感染症と診断された場合、抗菌薬による治療を開始してから24時間が経過し、かつ症状が改善していれば、登校・登園が可能とされています。ただし、施設ごとに異なる対応がある場合もあるため、医師や施設の指示に従ってください。
溶連菌感染症の予防方法はありますか?
溶連菌感染症の予防には、手洗いやうがいの徹底、感染者との密接な接触を避けることが重要です。また、感染者が使用した食器やタオルなどの共用を避け、家庭内での感染拡大を防ぐための対策を講じることが推奨されます。