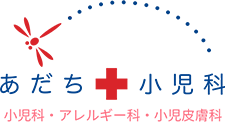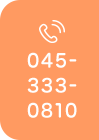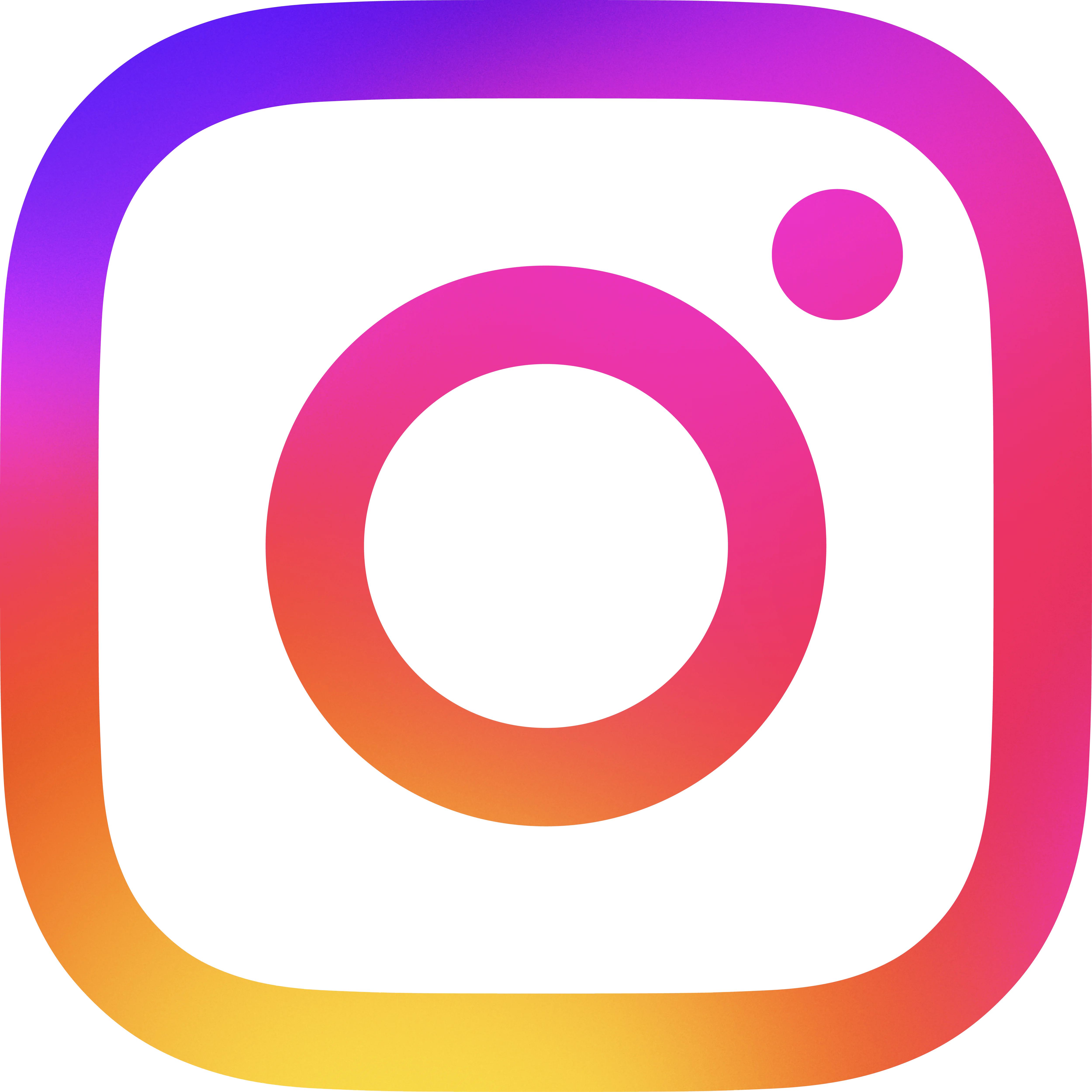ヘルパンギーナ
 ヘルパンギーナは、6月から初夏にかけて流行し、乳幼児に多く見られる夏風邪の代表的なウイルス性の感染症です。主に「コクサッキーウイルスA群」が原因ですが、ウイルスの型がいくつかあるので、何度もかかってしまうことも珍しくありません。まれに大人も発症します。
ヘルパンギーナは、6月から初夏にかけて流行し、乳幼児に多く見られる夏風邪の代表的なウイルス性の感染症です。主に「コクサッキーウイルスA群」が原因ですが、ウイルスの型がいくつかあるので、何度もかかってしまうことも珍しくありません。まれに大人も発症します。ヘルパンギーナの潜伏期間・症状
潜伏期間は、3〜6日です。
39℃以上の熱が1〜3日つづくと同時に、のどが赤く腫れて小さな水疱ができます。水疱は2〜3日でつぶれて黄色い潰瘍になります。
のどの痛みが強いために、食事が取り難くなることがあります。
ヘルパンギーナの治療
ヘルパンギーナは、ウイルスが原因で起こる夏かぜの一種です。現在のところ、原因ウイルスに直接作用する抗ウイルス薬は存在せず、治療は主に症状を和らげることを目的とした「対症療法」が中心になります。
熱や痛みへの対応
高熱が出ることも多いため、必要に応じて解熱剤(アセトアミノフェンなど)を使用することがあります。また、喉の奥にできた水疱や炎症により痛みが強く、食事や水分摂取が難しいケースもあります。お子さんがつらそうな場合は、痛み止めの使用も医師と相談しながら検討しましょう。
ご家庭での看護について
ヘルパンギーナはウイルスによる感染症のため、特効薬はなく、基本的には対症療法が中心です。回復までの期間、ご家庭でのケアがとても重要になります。
口内の痛みが強い時の食事の工夫
口の中に水疱や炎症ができていると、食べるたびに痛みを感じるため、無理に食事をさせる必要はありません。ただし、痛みを和らげつつ栄養とエネルギーを補うために、以下のような刺激の少ない食べ物をおすすめします。
- 冷たくて喉ごしのよいもの(プリン、ゼリー、アイスクリーム)
- 常温~やや冷ました柔らかい食事(冷ましたおかゆ、豆腐、ポタージュスープなど)
- 味付けは薄めにし、塩分・酸味・熱すぎるもの・硬いものは避けましょう
水分補給は最優先
食事よりもまず大切なのが水分補給です。脱水を防ぐことが、回復のカギになります。とくに高熱が続くと汗や呼気で水分が失われやすいため、こまめに飲ませましょう。オレンジジュースやスポーツドリンクなど酸味や糖分が強いものは、口の中にしみて痛みが悪化する場合があるため注意が必要です。 飲むのもつらいようなら、スプーン1杯ずつでも構いません。脱水が進むとおしっこの量が減るなどのサインが出るため、注意深く観察してください。
ヘルパンギーナの感染経路
ヘルパンギーナは、くしゃみなどの際に出る飛沫によって感染する「飛沫感染」と、舐めて唾液や鼻水がついたおもちゃの貸し借りなど、手が触れることで感染する「接触感染」が主な感染経路です。また、回復後も口(呼吸器)から1〜2週間、便から2〜4週間にわたってウイルスが排出されるので、おむつなどの交換後に汚染された手指を介して感染が広がります。
ヘルパンギーナ発症後の登園
保育園などの集団生活は解熱し、明らかな症状が改善していれば登園可能です。
よくある質問
ヘルパンギーナは何度もかかることがありますか?
はい、ヘルパンギーナは一度かかっても再感染する可能性があります。この病気の原因となるエンテロウイルスには複数の型があり、異なる型に感染することで再び発症することがあります。特に免疫力が未発達な乳幼児は、年に複数回かかることも珍しくありません。
ヘルパンギーナと手足口病の違いは何ですか?
ヘルパンギーナと手足口病は、どちらもエンテロウイルスによる夏に流行する感染症ですが、症状に違いがあります。ヘルパンギーナは突然の高熱とのどの奥に水疱ができるのが特徴で、手足には発疹が出ません。一方、手足口病は微熱や平熱で始まり、口の中や手足に水疱性の発疹が現れます。
ヘルパンギーナは大人にも感染しますか?
はい、ヘルパンギーナは大人にも感染する可能性があります。特に子どもから家庭内で感染するケースが多いです。大人が感染すると、子どもよりも症状が重く出ることがあります。感染予防のためには、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染対策が重要です。
ヘルパンギーナの潜伏期間はどれくらいですか?
ヘルパンギーナの潜伏期間は、通常3~5日程度です。感染後、突然の高熱やのどの痛みなどの症状が現れます。発症前からウイルスを排出していることもあるため、感染拡大を防ぐためには、日頃からの手洗いや咳エチケットが重要です。
ヘルパンギーナの予防接種はありますか?
現在、ヘルパンギーナに対する予防接種は存在しません。そのため、感染予防には手洗いやうがい、適切な咳エチケットなどの基本的な衛生対策が重要です。また、発症後も便からウイルスが排出されるため、おむつ交換後の手洗いなども徹底しましょう。
ヘルパンギーナで食事がとれないとき、どう対応すればよいですか?
ヘルパンギーナでは、のどの痛みが強くて食事や水分が摂れなくなることがあります。 このような場合は、刺激の少ない冷たいプリン・ゼリー・ポカリスエットなどで水分補給を優先しましょう。温かいものや酸味のあるものは痛みを強めることがあるため避けた方が無難です。 脱水症状が心配な場合は、すぐに医療機関を受診してください。お子さんの様子をよく観察し、「おしっこの回数が減った」「唇が乾いている」などのサインがあれば早めの対応が必要です。
ヘルパンギーナは保育園や家族内でうつりやすいですか?
はい、ヘルパンギーナは非常に感染力が強く、特に保育園や家庭内など密接な接触が多い環境では広がりやすいです。 主に「飛沫感染」や「接触感染」で広がるため、発症者の唾液や鼻水、便などに含まれるウイルスが手や物に付着し、それを介して感染することがあります。 手洗いやおもちゃ・食器の消毒、タオルの共用を避けるなど、家庭内での感染対策を徹底することが大切です。
 この記事は、
この記事は、
- 日本小児科学会(専門医)
- 日本アレルギー学会(専門医)
- 日本小児アレルギー学会
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 日本小児皮膚科学会
- 母子栄養協会 離乳食アドバイザー
黒岩 玲(あだち小児科 院長)が監修しています。