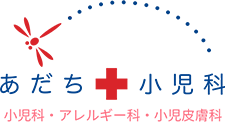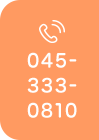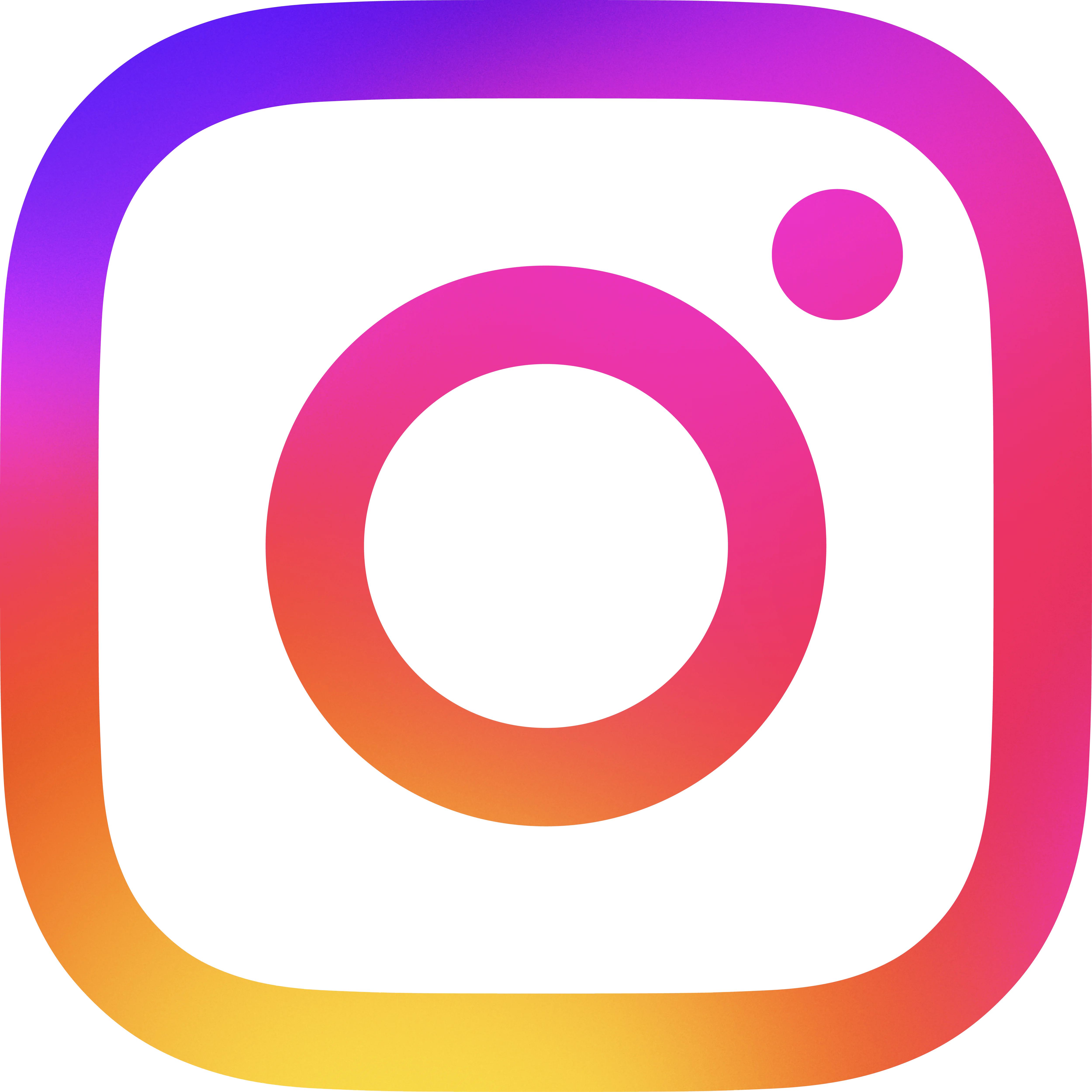嘔吐(おうと)について
嘔吐とは、胃が激しく収縮することで、胃の内容物を口から吐き出してしまうことです。子どもの場合、年齢によって対処方法や懸念される疾患が異なります。年齢といつから起こり、全身の状態はどのようになっているかなどを加味して判断することになります。
考えられる病気
赤ちゃん
授乳期の赤ちゃんの場合、まだ胃の入り口にある噴門がしっかりと発達していませんので、ちょっとした刺激でも吐き戻すことがあります。授乳の後にだらだらと吐いたり、ゲップが上手くできなくて吐いたりする場合は、特に異常とは言えません。
赤ちゃんがぐったりしている、顔色が悪い、熱が出ているなどの症状とともに嘔吐するようなら、代謝異常やミルクのアレルギー、消化管閉塞、脳出血などが考えられますので、急いで診療を受けましょう。
幼稚園児
幼稚園児の場合、激しい咳によって吐き戻してしまうこともありますが、ほとんどは感染性の急性胃腸炎によるもので、原因としてはアデノウイルス、ノロウイルス、ロタウイルスなどのウイルスによるものがほとんどです。
また、嘔吐の前に頭を打っているような場合は、頭部外傷や脳出血を心配する必要があり、その他にも髄膜炎、腸重積症などの他、中耳炎、尿路感染症、鼠径ヘルニア嵌頓などが考えられます。
ぐったりしている、顔色が悪い、吐瀉物に血が混じっている、血便がある、おしっこが長時間出ていないなどの場合、すぐに医療機関に相談してください。
小学生
小学生の時期でも、一番多いのはウイルス性の急性胃腸炎です。その外には2歳頃に発症し、10歳頃まで続く周期性嘔吐症候群は、周期的に発作的な嘔吐を繰り返すのが特徴の疾患で、中学年ぐらいまでに見られることがあります。
また、溶連菌やアデノウイルスによる咽頭炎でものどの痛みから吐き戻してしまうことがあります。その他では、片頭痛によるもの、重篤なものでは、十二指腸潰瘍や上腸間膜動脈症候群、脳腫瘍なども考えられます。
さらに思春期を迎えると、過敏性腸症候群などの他、自律神経調節性障害や起立性調節性障害といった自律神経系の異常によって嘔吐することもあります。
ウイルス性胃腸炎で嘔吐している場合の対応
ウイルス性の急性胃腸炎は、いわゆる「お腹の風邪」と表現されるような状態です。ウイルスに対して抗菌薬は効果を発揮できませんので、基本的には安静と嘔吐や下痢による脱水を防ぐための水分補給を中心に対処します。嘔吐した後、2時間程度は飲食を控えます。その後給水を開始する際も、一度に大量に飲ませず、少量ずつゆっくりと飲ませるようにしてください。経口補水液が望ましいのですが、水やお茶でもかまいません。
嘔吐が続く場合などは、対症療法として制吐剤の坐薬などを処方することもあります。
嘔吐を繰り返し水分が補給できない、ぐったりしている、顔色が悪い、血便が出る、おしっこが長時間出ないといった場合は、速やかに医療機関を受診してください。
また、吐瀉物にはウイルスが混ざっていて、感染を広める原因となってしまうこともあるため、ビニール手袋をしての清掃、消毒、清掃後の手洗いを行いましょう。
嘔吐物から大人もうつる?
お子さんが嘔吐をした際、「これって家族にもうつるの?」と不安に思う保護者の方も多いのではないでしょうか。特に、ウイルス性胃腸炎(ノロウイルスやロタウイルスなど)が原因の場合、嘔吐物や便からの二次感染が起こる可能性があります。
どうやってうつる?
大人への感染は、主に次のような経路で起こります。
- 嘔吐物や便に触れた手で口や鼻に触れる
- 嘔吐時の飛沫を吸い込む
- ウイルスが付着したタオルやおもちゃ、ドアノブなどを介した間接接触
症状がないままウイルスを排出する「不顕性感染(ふけんせいかんせん)」もあるため、見た目が元気であっても感染源になっている場合もあります。
嘔吐と一緒に下痢を起こすこともある?
お子さんが突然嘔吐し、続けて下痢が始まると、ご家族は大変心配になることと思います。嘔吐と下痢は、同時に起こることが珍しくなく、特に「感染性胃腸炎」などの消化器の不調が原因となっているケースが多くみられます。
嘔吐と下痢が一緒に起こる主な原因
- ウイルスや細菌による感染性胃腸炎
最も一般的なのが、ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなどのウイルス、またはサルモネラ菌やカンピロバクターなどの細菌による腸の感染です。これらの病原体が胃や腸に炎症を起こし、吐き気・嘔吐・腹痛・下痢を引き起こすことがよくあります。 園や学校など集団生活をしているお子さんでは、流行する時期には特に注意が必要です。
- 食中毒
加熱が不十分な食品や衛生状態の悪い食べ物を摂取すると、食中毒が起き、激しい嘔吐と下痢を伴うことがあります。症状は突然始まり、数時間以内に強まる傾向があります。
- 慢性的な腸の炎症性疾患
小児では頻度は高くないものの、クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患によって、**下痢とともに吐き気や嘔吐が生じることもあります。これらは慢性化することがあるため、長引く症状がある場合は専門的な診察が必要です。
- 未発達な胃腸の反応
乳幼児は、胃腸の働きがまだ成熟しきっていないため、ちょっとしたウイルス感染や食事の変化でも、嘔吐や下痢が同時に起こることがあります。発熱や機嫌、食欲なども含めて総合的に見て判断することが大切です。
受診の目安
- 嘔吐や下痢が数日以上続く
- 水分がとれない、尿が出ない、ぐったりしている
- 血便が出ている、強い腹痛がある
- 嘔吐の中に血液や緑色の液体が混じる
これらの症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
夜間や休日に嘔吐した時のホームケアポイント
嘔吐後には水分を飲ませないでください。
1~2時間様子を見て吐かないことを確認してから、常温んの水分の摂取を一口ずつから試みてください。(目安10~15ml)はじめは白湯から、子供用のイオン水や経口補水液でもかまいません。
徐々に水分量を増やし、水分でも嘔吐しないことを確認したら、消化の良いものを食べ始めてください。水分が摂取できないと、固形物は摂取できません。
翌日当院をご受診ください。様子をみても、嘔吐を繰り返す、おしっこが減っている、ぐったりしているときは#7119におかけになり様子をご相談いただくか、救急病院をご受診ください。
救急時の連絡先
| 救急相談センター | #7119 または 045-232-7119(24時間) |
|---|---|
| 保土ヶ谷区休日診療所 | 045-335-5975(日曜祝祭日年末年始10:00~16:00) |
| 横浜市夜間救急センター | 045-212-3535(20:00~24:00) |
| 横浜市民病院 | 045-316-4580 |
※かかりつけ医にご登録の方は専用電話をご利用下さい。
よくある質問
子どもが嘔吐や下痢をしていますが、熱がない場合でも受診は必要ですか?
はい、発熱がなくても症状が続いている場合や水分がとれない場合は受診をおすすめします。 ウイルス性胃腸炎などは、熱を伴わないこともあります。ぐったりしている、食事や水分を受けつけない、下痢や嘔吐が数日続くなどの症状があるときは、早めにご相談ください。
子どもの嘔吐や下痢は家族にうつりますか?看病するうえで気をつけることは?
感染性の場合、大人や兄弟にうつることがあります。 特にノロウイルスなどは、嘔吐物や便に含まれるウイルスが強い感染力を持っているため注意が必要です。手洗いの徹底、使い捨て手袋・マスクの着用、消毒などを心がけましょう。
嘔吐や下痢が長引いていますが、何日ぐらい様子を見てよいですか?
症状が2〜3日以上続く場合や、繰り返し戻す・ぐったりしている様子があれば、早めに受診をおすすめします。 特に乳幼児は脱水になりやすいため、長引く下痢や嘔吐は自己判断せず、早めに当院へご相談ください。
吐いた後や下痢のあと、食事はどうしたらいいですか?
最初は無理に食べさせず、まずは水分補給を優先しましょう。 落ち着いてきたら、おかゆ、うどん、すりおろしたりんご、バナナ、にんじんの煮物など、消化に良い食べ物を少量ずつ与えると安心です。乳製品や油っこい食べ物はしばらく避けましょう。
子どもが下痢のときに、看病している大人が特に気をつけることはありますか?
嘔吐や便の処理時には、手袋とマスクを着用し、処理後の手洗いと消毒を徹底しましょう。
また、使用したタオルや衣類は別に洗濯し、可能であれば使い捨ての物品を使うとより安心です。看病の際に顔を近づけすぎない、食事を一緒に取らないなどの配慮も大切になります。
嘔吐や下痢のときに受診の目安となる症状はありますか?
以下のような症状がある場合は、すぐに受診してください。
◆水分がとれない、尿の回数が極端に少ない
◆血便が出ている、強い腹痛がある
◆嘔吐が繰り返し起こる、吐いたものに血や緑色の液が混じる
◆意識がぼんやりしている、ぐったりして反応が鈍い
ノロウイルスやロタウイルスにかかったら、いつから登園・登校していいですか?
症状が完全に落ち着き、しっかり食事や排便が安定してからの登園・登校が目安となります。 具体的には、下痢・嘔吐が治まってから少なくとも24〜48時間以上経過し、元気が戻っていることが望ましいです。園や学校の規定によって異なる場合がありますので、医師の診断とあわせてご確認ください。
 この記事は、
この記事は、
- 日本小児科学会(専門医)
- 日本アレルギー学会(専門医)
- 日本小児アレルギー学会
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 日本小児皮膚科学会
- 母子栄養協会 離乳食アドバイザー
黒岩 玲(あだち小児科 院長)が監修しています。