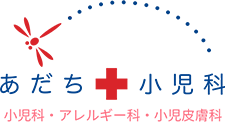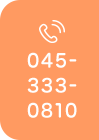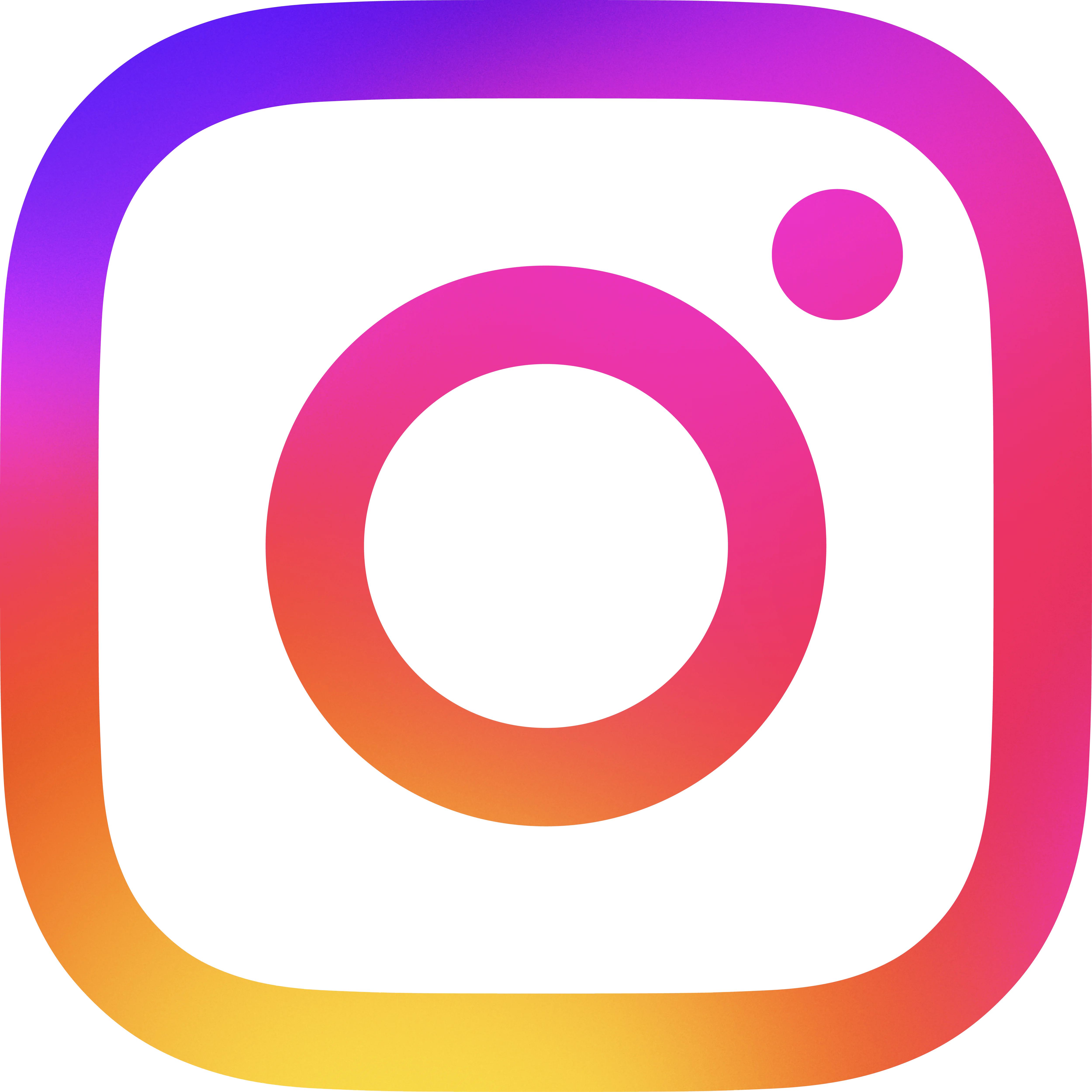下痢について

通常、便は大腸で水分をある程度吸収され、固形成分によって適切な硬さを保って排泄されます。しかし何らかの理由で水分が多くなると軟便や水様便になります。下痢は成人の場合は軟便から水様便の状態が1日に3回以上ある場合と定義されていますが、子どもの場合は腸の機能が発育途上にあるため、回数が多くても腹痛などの症状がなければ心配する必要がないことも多いです。しかし、軟便や水様便がいつまでも続いたり、極端に回数が多かったりする場合などは、下痢によって水分が失われて脱水を起こしてしまうこともあります。
下痢が長く続いている、便の色や形がいつもと極端に異なる、発熱や嘔吐、腹痛などを伴っている、体重が減っているなどの場合、注意が必要です。心配なことがあれば、いつでもご相談ください。
下痢が長引く理由
お子さんの下痢が数日で治まらず、何日も続いていると、「大丈夫かな?」と不安になると思います。 子どもの下痢にはさまざまな原因があり、体調や食生活、環境などが複雑に関係しています。特に1週間以上下痢が続く場合や、血便・発熱・ぐったりしている様子が見られるときには、医師の診察を受けることが大切です。
下痢が長引く主な原因
- 消化機能の未熟さ
幼児期や学童期の子どもは、まだ消化器官が発達途中です。脂っこい食べ物や消化の悪いものを食べると、腸に負担がかかり、下痢を起こすことがあります。
- ウイルス・細菌感染
ロタウイルスやノロウイルスなどによるウイルス性胃腸炎、または食中毒の原因菌による細菌性胃腸炎は、激しい下痢を引き起こします。集団生活をしている年齢の子どもには特に多い原因です。
- 食物アレルギー
乳製品や卵、小麦、果物など、特定の食品に対するアレルギー反応が腸に出て、下痢が慢性的に続くことがあります。
- 慢性腸疾患
過敏性腸症候群(IBS)や、クローン病・潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患が原因で、慢性的に下痢が起こることも。学童期や思春期以降に発症することがあります。
- 便秘による二次的な下痢
腸に便がたまっていると、液状の便がすき間から漏れ出す「漏出性下痢」が起こることがあります。見た目には下痢ですが、実は便秘が原因というケースも。
- 薬の副作用
抗生物質などの薬を服用した後、腸内の善玉菌が減って下痢を起こすことがあります。
- 二次性乳糖不耐症
胃腸炎の回復途中などに腸の粘膜が弱っていると、乳糖をうまく消化できず、牛乳やヨーグルトで下痢が続くことがあります。
- 心理的要因・ストレス
登園や登校の不安、人間関係のストレスなどが影響して、腸の働きが乱れ、下痢が続くことがあります。特に感受性が強いお子さんに見られます。
主な対処法
下痢が続く場合、大切なのは脱水を防ぐことです。水分補給はこまめに行い、経口補水液(ORS)など電解質を含む飲み物をとってください。食事は無理をせず、おかゆやうどんなど消化の良いものを少量ずつ摂るように心がけます。牛乳や油分の多い食品は、症状を悪化させる場合があるため一時的に控えるのが無難です。また、下痢が1週間以上続く場合や、血便・発熱・ぐったりしている様子が見られる場合は、自己判断せずに早めに受診してください。アレルギーや乳糖不耐症、薬の副作用が疑われる場合には、医師の指導のもとで検査や食事調整を行うことが大切です。症状が落ち着いた後も、腸内環境を整えるために、ヨーグルトや発酵食品、食物繊維を含む野菜などを少しずつ取り入れていくとよいでしょう。
大人にもうつる?
お子さんがウイルス性胃腸炎などで下痢や嘔吐をしていると、「家族にうつるのでは?」と心配になることも多いのではないでしょうか。特に小さなお子さんは、自分での衛生管理が難しいため、看病するご家族に感染が広がるケースも少なくありません。ウイルス性の胃腸炎(ノロウイルスやロタウイルスなど)の場合、大人も感染することがあります。 ウイルスは、お子さんの便や嘔吐物に多く含まれており、手や物を介して口に入ることで感染が成立します。特に看病中の接触が多い保護者は、注意が必要です。主な感染経路
- 接触感染
ウイルスが付着した手やおもちゃ、タオル、ドアノブなどを介して、口にウイルスが入ることで感染します。おむつ交換や嘔吐物の処理の際にリスクが高まります。
- 飛沫感染 嘔吐や咳、会話などで発生した飛沫が空気中に広がり、それを吸い込むことで感染することもあります。嘔吐時の処理時は特に注意が必要です。
感染予防
大人への感染を防ぐためには、日常のちょっとした衛生管理が重要です。- 石けんと流水による丁寧な手洗いを徹底しましょう。特におむつ交換後、食事前、調理前などは忘れずに。
- 嘔吐物や便の処理は、使い捨ての手袋やマスクを着用し、処理後は次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤など)でしっかり消毒を行います。
- タオルや食器は共有せず、感染者専用に分けて使用しましょう。 飛び散った床や周囲の壁は、使い捨てペーパーで拭き取り、消毒剤で二度拭きするのが望ましいです。 看病中もこまめに換気を行い、マスクの着用や咳エチケットも意識しましょう。
考えられる疾患
急性下痢症
急性下痢症は突然腹を下した状態になり、一般的に1週間以内で症状が治まるものです。原因は細菌やウイルスなどの感染性のものと、非感染性のものに分けられます。
感染性のものはウイルス感染によるものが多く、原因となるウイルスは、アデノウイルス、ノロウイルス、ロタウイルスなどがあります。また、細菌によるものでは、サルモネラ菌、カンピロバクター、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌などがあります。
一方、非感染性の下痢の多くは食物アレルギーや薬剤の副作用によるものなどが考えられます。
慢性下痢症
下痢状態が2週間以上続いている場合、慢性下痢症と言います。さまざまな原因が考えられますので、症状などによって推測しながら、詳細な検査を行って原因を特定します。
考えられる疾患としては、過敏性腸症候群、難病に指定されている炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)、ホルモン産生腫瘍などが考えられます。
ウイルス性胃腸炎
ウイルスの場合抗菌薬が効かないため、対症療法を中心に治療します。治療の内容は、下痢に伴う脱水症状の程度によって異なります。
脱水症状が軽度から中等度であれば、整腸剤などを服用させながら経口補水液で給水し、経過観察ですみますが、中等度から高度の脱水がある場合は、経口による保水も難しいケースがあるため、入院して点滴で水分を確保する必要があります。
原因となるウイルスや細菌の種類
下痢の原因となるウイルスや細菌にはさまざまな物があります。以下に代表的なものを表にしましたので、参照してください。
| 病原体名 | 流行期 | 潜伏期間 | 便の性状 | 下痢の継続期間 |
|---|---|---|---|---|
| アデノウイルス | 通年(夏>冬) | 7~8日 | 水様便 | 7~10日間 |
| ノロウイルス | 冬 | 24~48時間 | 水様便で特有の臭いがあります | 12~48時間 |
| ロタウイルス | 冬 | 48~72時間 | 水様便で特有の臭いがあります | 2~10日間 |
| サルモネラ菌 | 春から夏にかけて | ~72時間 | 水様便や粘血便 | ~7日間 |
| カンピロバクター | 通年ですが初夏に多い傾向があります | 1~7日 | 水様便や粘血便 | ~7日間 |
| 腸管出血性大腸菌 | 通年 | 2~7日 | 血便 | ~2週間 |
よくある質問
中等度の脱水になると注意が必要と言われましたがどんな症状ですか?
ぐったりしていて。尿量がかなり減っている、口や舌に乾燥が見られるような状態で、体重も5%~10%減ってきたら中等度の脱水の可能性があります。すぐに受診するようにしましょう。
ウイルス性胃腸炎による下痢と診断されたら、母乳による授乳は中止するべきでしょうか?
ウイルス性腸炎の場合、絶食は推奨されていませんので、母乳はそのまま続けて飲ませてください。
ウイルス性胃腸炎による下痢と診断されたら、人工乳栄養は中止すべきでしょうか?
母乳と同様、人工栄養もそのまま続けてください。以前は下痢の場合人工乳は希釈した方が良いとされていましたが、最近の研究で希釈には意味がないことがわかってきました。その上で経口補水液などによる給水も心がけてください。
消化の良い食事を摂るように言われました。どんなものがありますか?
同じ食材でも、焼くより、煮込んだり蒸したりすると消化がよくなります。
食べものとしては、おかゆ、煮込んだうどん、柔らかく煮た野菜や蒸し野菜、暖かい豆腐、半熟卵などの他、動物性たんぱく質では鶏肉のささ身や白身魚、りんごのすり下ろし、バナナ、牛乳やスポーツドリンクなどがよいでしょう。ただし牛乳やスポーツドリンクなどもあまり冷たいものは避けて常温程度にぬるめて飲んでください。
子どもが下痢のときに、看病している大人が特に気をつけることはありますか?
嘔吐や便の処理時には、手袋とマスクを着用し、処理後の手洗いと消毒を徹底しましょう。
また、使用したタオルや衣類は別に洗濯し、可能であれば使い捨ての物品を使うとより安心です。看病の際に顔を近づけすぎない、食事を一緒に取らないなどの配慮も大切になります。
子どもが回復した後も、大人に感染するリスクはありますか?
はい、症状が治まってからもしばらくは便の中にウイルスが排出されることがあります。 特にノロウイルスの場合は、回復後も1週間程度は感染力があるとされています。トイレ後の手洗いやトイレの消毒など、完治後も一定期間の感染対策は必要です。
子どもが使った食器やタオルはどう扱えばいいですか?
感染予防のため、食器は別にして洗浄・消毒し、タオルや衣類も分けて洗うのが望ましいです。 熱湯消毒や漂白剤を使った処理が効果的です。タオルは使い捨てペーパータオルに替えると、感染リスクをさらに抑えられます。
大人に感染した場合、子どもと症状は異なりますか?
基本的な症状(下痢・嘔吐・腹痛など)は似ていますが、大人の方が脱水や疲労感を強く感じやすい傾向があります。 また、高齢者や体力が低下している方は、重症化のリスクが高くなるため要注意です。感染した場合は無理をせず、必要に応じて医療機関を受診しましょう。
 この記事は、
この記事は、
- 日本小児科学会(専門医)
- 日本アレルギー学会(専門医)
- 日本小児アレルギー学会
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 日本小児皮膚科学会
- 母子栄養協会 離乳食アドバイザー
黒岩 玲(あだち小児科 院長)が監修しています。