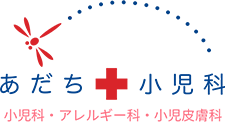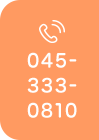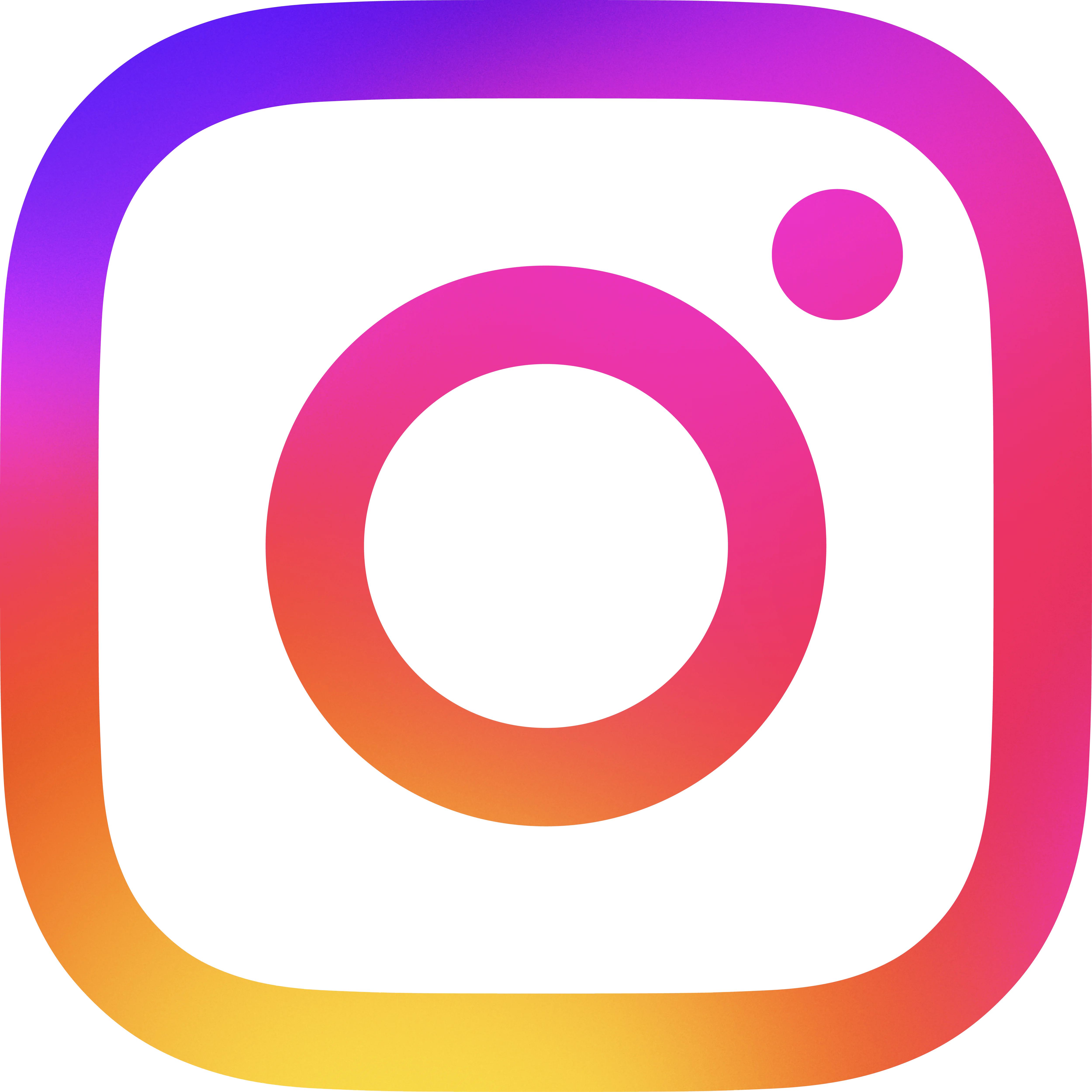手足口病
 手足口病は夏季に流行し、7月にピークを迎えるウイルス性の感染症です。原因ウイルスは「エンテロウイルス」と「コクサッキーウイルス」で、それぞれのウィルスには複数の種類があるので何度もかかる可能性もあります。患者のほとんどは小児で、5歳未満の小児が80%を占めますが、まれに大人にも感染します。
手足口病は夏季に流行し、7月にピークを迎えるウイルス性の感染症です。原因ウイルスは「エンテロウイルス」と「コクサッキーウイルス」で、それぞれのウィルスには複数の種類があるので何度もかかる可能性もあります。患者のほとんどは小児で、5歳未満の小児が80%を占めますが、まれに大人にも感染します。手足口病の潜伏期間と症状
潜伏期間は、3〜6日で、口の中の粘膜や手のひら、足の裏、足の甲などに水疱性の発疹や紅色発疹が散在します。膝やひじの外側、臀部陰部にも出現します。1〜3日間発熱することがあります。水疱が大きくなるとかさぶたになってから治るタイプと、赤い発疹が中心でそのまま消失していくタイプがあります。発疹は1週間程度でなくなりますが大きく水泡化すると改善までに2~3週間かかる場合があります。また、1〜2ヶ月後に手足の爪がはがれることがありますが、大事にはいたらずすぐに新しい爪が生えてきます。
口の中にできた水疱がつぶれた後にできる口内炎(口の中にできた潰瘍)がひどく、痛みで食事や飲みものを受けつけなくなることもあります。また、原因ウイルスの「エンテロウイルス」は無菌性髄膜炎の90%を占めるため、まれに脳炎を伴って重症化することもあるので注意が必要です。
手足口病の合併症について
手足口病は多くの場合、数日で自然に回復する軽症のウイルス感染症ですが、まれに深刻な合併症を引き起こすケースもあるため、注意が必要です。
無菌性髄膜炎:長引く発熱や頭痛に注意
特に気をつけたい合併症が「無菌性髄膜炎」です。これはウイルスの影響で脳を包む膜に炎症が起こる状態で、強い頭痛、発熱、吐き気、嘔吐などがみられることがあります。重症化すると意識がもうろうとしたり、ぐったりするなどの神経症状が出ることもあります。
目安
高熱が3日以上続く、頭痛が強くなる、普段と違う様子が見られる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
心筋炎・脳炎:極めてまれだが注意だが必要
一部のウイルス株では、心筋炎(心臓の筋肉に炎症が起こる)や脳炎(脳自体の炎症)といった合併症が報告されています。頻度は非常に低いものの、発症すると急激に容態が悪化することがあります。
目安
呼吸が苦しそう、顔色が悪い、意識がぼんやりするなどの異変があれば、迷わず受診してください。
脱水症状:口の痛みで水分不足に
手足口病では、口の中の水疱(みずぶくれ)や潰瘍が痛むことで、食事や水分を嫌がるお子さんが多く見られます。その結果、水分摂取が不十分となり脱水に陥る危険性があります。特に乳幼児では進行が早いため、こまめな水分補給が重要です。
目安
尿の量が少ない、口の中が乾いている、ぐったりしている場合は脱水のサインです。
手足口病の治療について
手足口病はウイルスによって引き起こされる感染症であり、ウイルスそのものを排除する特効薬はありません。そのため、治療は基本的に「対症療法(症状をやわらげるケア)」が中心となります。多くの場合は、特別な医療処置をせずとも数日から1週間ほどで自然に回復していきます。
発熱や痛みに対する対応
高熱が出る場合は、解熱剤(アセトアミノフェンなど)でつらさを軽減します。また、口の中の水疱やただれが強いと、食事や水分が取りづらくなります。そうした場合には、痛みをやわらげる鎮痛薬や、刺激の少ない食事の工夫が有効です。
水分補給が最優先事項
特に注意したいのが、脱水のリスクです。口の痛みで飲食を拒むと、体内の水分が不足しやすくなります。麦茶、冷ましたスープ、ゼリー、アイスクリームなど、のどごしが良くてしみないものを選ぶと摂取しやすくなります。食欲がなくても、水分がしっかり摂れていれば大きな問題にはなりません。
皮膚の発疹や水疱への対応
手足にできる発疹や水疱は、多くの場合そのままでも自然に治ります。ただし、かゆみや不快感が強い場合には、保湿剤や必要に応じてかゆみ止めの外用薬を使うことがあります。また、水疱をひっかくと化膿したり二次感染を起こす可能性もあるため、爪を短く切り、肌を清潔に保つことも大切です。
水分補給が最優先事項
特に注意したいのが、脱水のリスクです。口の痛みで飲食を拒むと、体内の水分が不足しやすくなります。麦茶、冷ましたスープ、ゼリー、アイスクリームなど、のどごしが良くてしみないものを選ぶと摂取しやすくなります。食欲がなくても、水分がしっかり摂れていれば大きな問題にはなりません。
家庭でのケアと登園・登校の注意点
手足口病は家庭での安静とケアが治療の基本ですが、自己判断での薬の使用は避け、医師の診断を受けて適切な指示を仰ぐことが重要です。軽症でも、集団生活を送る子どもは感染拡大を防ぐために、症状が落ち着くまで登園・登校を控えるようにしましょう。
よくある質問
手足口病の発疹はかさぶたになりますか?あとが残ることはある?
手足口病の発疹は通常、かさぶたにならず自然に消えていくことがほとんどです。ただし、発疹が強く出たり、かきむしったりしてしまうと色素沈着や軽いあとが残ることがあります。発疹が気になる場合でも、無理に触らず清潔を保ち、自然に治るのを待ちましょう。万が一、発疹のあとにしこりや痛みが残るようであれば、小児科を受診してください。
手足口病のあとに爪がはがれました。異常ではない?
手足口病の回復後、1〜2か月ほどして手や足の爪が自然にはがれることがあります。これは「爪甲脱落症(そうこうだつらくしょう)」と呼ばれ、ウイルス感染による一時的な爪の成長障害が原因と考えられています。見た目には驚くかもしれませんが、多くの場合は自然に新しい爪が生えてくるため、心配はいりません。痛みや炎症がある場合には、早めに医師の診察を受けましょう。
手足口病と診断されたら入浴はしていい?注意点は?
発熱がなく、元気があるようであれば基本的に入浴は可能です。ただし、発疹が痛んだり皮膚に傷がある場合は、ぬるめのお湯にして刺激を避けるようにしましょう。石けんでやさしく洗い、ゴシゴシこすらないことが大切です。また、他の家族への感染を防ぐため、タオルやバスタブの共用は控えるのが望ましいです
手足口病は何度もかかる病気ですか?
はい、手足口病は一度かかっても再びかかることがあります。原因となるウイルスは複数の種類(主にコクサッキーウイルスやエンテロウイルスなど)があるため、違うウイルスに感染すれば再発します。前回と症状の現れ方が異なることもあるため、「以前かかったからもう大丈夫」と思わず、感染予防は継続しましょう。
手足口病と水ぼうそうやとびひはどう見分ければいい?
手足口病の発疹は、口の中・手のひら・足の裏に多く現れるのが特徴です。水ぼうそうは体全体にかゆみを伴う水ぶくれができ、とびひは膿をもった水疱やかさぶたが顔や手足に広がります。発疹の場所や形、かゆみの有無である程度区別できますが、自己判断が難しい場合は小児科での診察をおすすめします。適切な治療のためにも正確な診断が重要です。
手足口病のときに避けた方がいい食べ物はありますか?
はい、のどや口内に痛みを伴う発疹があるため、刺激の強いものは避けた方がよいです。辛いもの、熱いもの、酸っぱい果物(オレンジ・パイナップルなど)や塩分の強いスナック類は、痛みを悪化させる可能性があります。口当たりの良いゼリー・プリン・冷ましたうどんなど、刺激の少ない食事が適しています。水分補給も忘れずに行いましょう。
手足口病は大人にも感染しますか?どんな症状が出る?
手足口病は大人にも感染することがあります。特に小さな子どもと接する機会の多い保護者や保育士の方は注意が必要です。大人がかかると、子どもよりも強い喉の痛みや発熱、全身倦怠感が出ることがあります。また、発疹も痛みを伴いやすく、症状が重くなるケースも。感染予防のために、タオルや食器の共有を避け、手洗い・うがいを徹底しましょう。
 この記事は、
この記事は、
- 日本小児科学会(専門医)
- 日本アレルギー学会(専門医)
- 日本小児アレルギー学会
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 日本小児皮膚科学会
- 母子栄養協会 離乳食アドバイザー
黒岩 玲(あだち小児科 院長)が監修しています。