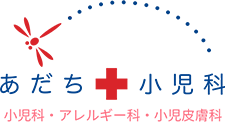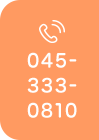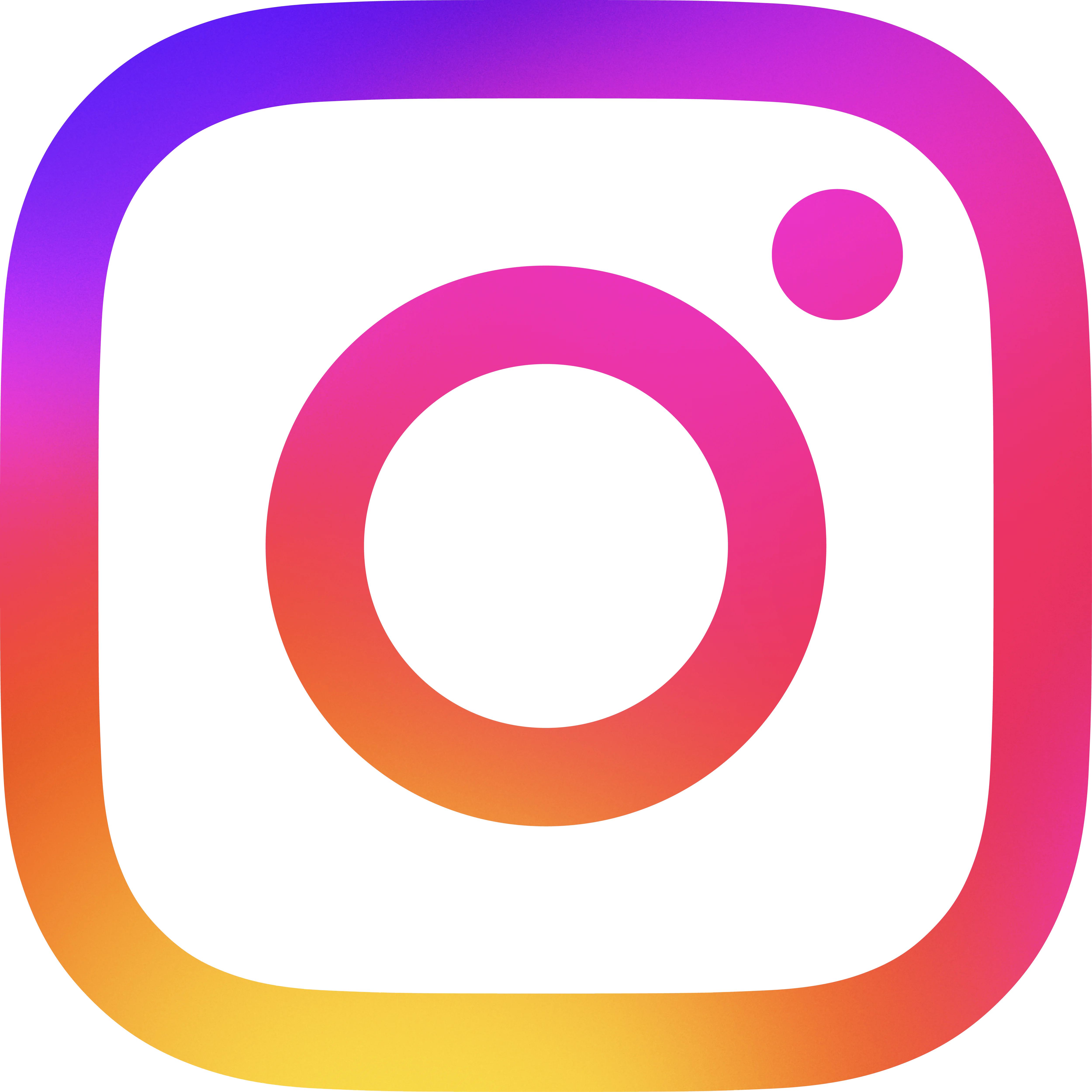便秘について

子どもは消化器の機能が発達途上にありますので、よく便秘をすることがあります。
便秘とは、長い間便が出ない状態、または快適に充分な量の便が出せない状態のことを指しています。
大便の回数が週に3回以下、または5日以上出ない状態か、毎日便が出ていたとしても、少量ずつ何度かに分けて出たり、コロコロとしたウサギの糞のような便だったりする、または便が出るときに痛がる様子を見せたり、肛門が切れて血が滲むようなことがある場合も便秘の疑いがあります。
乳幼児の場合、一人一人で便の回数や形態なども様々です。また離乳の時期やトイレの練習を開始する時期などによっても異なってきます、また、幼児期になっても成長の度合いはそれぞれですので、保護者の方も自分の子どもが正常な状態なのか便秘なのかについては迷うことも多いと思います。
便秘というと、それほど重篤な病気ではないと思われがちです。一般的には、短期間の治療で解決することも多いのですが、時には難治性の便秘もあります。その場合、放置してしまうと腸内フローラがしっかりと形成できなくなるようなことや、さらに重症の場合、直腸周辺に硬い便が溜まって、しっかりした便が出なくなり、その隙間を縫って軟便がいつも漏れてしまうような状態になることもあります。このような状態になる前にきちんと治療をする必要もあります。
これらは、他に原因となる疾患のない「機能性便秘」ですが、その外にも、腸に生まれつきの異常がある、内分泌系統に問題がある、代謝に問題があるなど、何らかの疾患があって便秘を起こしていることもあります。
子どもの状態をしっかりと診察するとともに、保護者の方のお話も丁寧にお訊きして、個々の状態にあわせて、最適の治療法を提案していきます。子どもの便についてお悩み事があれば、いつでもご相談ください。
こんな症状に気付いたらお気軽にご相談ください
- 何日も大便が出ない状態が続く
- 便が硬くコロコロしたウサギの糞のような状態が続く
- 便をするときに痛がる、苦しそう
- お腹を触ると張っていて硬い
- 便やおならが普段より臭う
- 授乳してもすぐ吐いてしまう
- 食欲がなく、あまり食べない
- 排便時に血が出る など
発熱を伴う便秘にご注意ください
子どもが便秘のときに、「なんとなく元気がない」「食欲が落ちている」といった変化が見られることがあります。実は、便秘そのものが原因となって、体温が一時的に上がることもあるのです。腸に便がたまり続けることで腸内環境が悪化し、38度台の熱を伴うことも珍しくありません。 一方で、「毎日排便があるから便秘ではない」と思われる保護者の方もいらっしゃいますが、量が少ない、硬い、出しきれない感覚があるなどのケースでも、実際には便秘状態であることがあります。 便秘と発熱が同時に見られた場合は、腸内の不調が関係している可能性もあるため、単なる発熱と見過ごさず、当院にご相談いただくことをおすすめします。
お子様の状態を見極めた治療
子どもの便秘では、生活習慣や食生活によるものか、他に治療が必要な基礎疾患がないかなどをきちんと見極める必要があります。まだ小さなうちは、自分で症状を話すことができませんので、保護者の方による観察も大切です。しっかりとお話をお訊きした上で、基礎疾患があると考えられる場合は、検査などで診断し、その治療を行います。また生活習慣などから起こっている場合は、食生活や睡眠、運動などについての指導や、トイレの練習の仕方などをお伝えします。それぞれの子どもに合った、治療方針を建て、本人にも保護者の方にもつらくない治療を目指しています。
当院の治療方針
当院では、本人、保護者の方など、関係した皆さんが、良い状態の便を適切な量だけ、快適に出せるようになったと、納得していただける状態を便秘治療の目標と考えています。
そのために、正しい排便習慣を身につけるための練習を行う必要があります。それは子どもの年齢、成長度合い、体力などによって一人一人異なるため、個々の状態に合わせたメニューを組み立てていく必要があります。
便秘の治療は、短期間で終わるものではなく、時をかけてじっくりと取り組む必要があります。
しかし、それだけでは本人も保護者の方もどうしても飽きてしまうことや、焦りが出てくることもありますので、長期の目標に到達するために、短期間で達成できる過程を設けて、それらを少しずつ達成することで、モチベーションを保つような工夫もしております。
便秘は心理的な要素も関係しています。快適に排便ができるようになり、「ああ、ちゃんと治療を続けていてよかった」と思えるような治療を目指しておりますので、子どもの便に関するお悩みがある時はお気軽にご相談ください。
年齢による便秘の違い
子どもの便秘は、年齢や成長の段階によって原因や対策が異なります。とくに乳児期や学童期では、生活習慣の変化や排便リズムの乱れがきっかけになることも多いため、注意が必要です。
乳児期の便秘
離乳食を始める頃から、赤ちゃんの便の性状や排便の回数に変化が出てくることがあります。水分量や食物繊維の摂取が少ないと、便が硬くなりやすく、うまく排便できないことも。そのため、離乳期から便秘の兆候が見られる場合は注意が必要です。 また、離乳食前の生後3ヶ月未満の赤ちゃんで便秘が続く場合は、消化器官や神経の発達異常など、身体の構造的な問題が隠れている可能性もあります。出生後に便が出にくい、あるいはお腹が張って苦しそうな様子が見られる場合には、早めに医療機関を受診することが重要です。
幼児〜学童期の便秘
トイレトレーニング期(2〜3歳頃)や、小学校入学前後になると、排便を我慢してしまうことが原因で便秘が悪化するケースが増えてきます。たとえば、「朝は忙しくてトイレに行く時間がない」「学校のトイレが使いにくい」「人目が気になる」といった心理的な要因で、便意を感じても排便を控えることがあります。 さらに、朝食を抜く習慣も腸の動きを鈍らせ、排便リズムを乱す原因になります。朝食は腸を刺激して自然な排便を促す役割があるため、しっかり食べることが便秘予防にもつながります。
対処法
子どもの便秘を改善するためには、日常生活の見直しが非常に重要です。以下のポイントを参考に、まずはできるところから取り組んでみましょう。
規則正しい生活習慣
便秘を改善するためには、生活リズムを整えることが基本です。朝はできるだけ早く起き、朝食をしっかりとることで、体を目覚めさせることができます。また、トイレに行く習慣をつけることも大切です。例えば、朝起きたら最初にトイレに行くという簡単な習慣から始めるだけでも、便秘解消に繋がることがあります。夕食はできるだけ早めに済ませ、寝る時間を一定にすることで、体内時計が整い、便秘の予防にもつながります。急に生活習慣をすべて変更するのは難しいかもしれませんが、少しずつ取り組むことが大切です。
バランスの取れた食事
便秘の改善には、特定の食品をたくさん摂るよりも、栄養バランスの取れた食事が重要です。食物繊維や水分は確かに便秘に効果がありますが、過剰に摂取することが必ずしも効果的とは限りません。研究によると、便秘のある子どもとそうでない子どもの間で、食物繊維や水分の摂取量に大きな差がないことが示されています。つまり、食事は偏らず、いろいろな種類の食品を取り入れ、バランスよく食べることが肝心です。無理に食べさせるのではなく、楽しく栄養が豊富な食事を心掛けることが、便秘の改善を促進します。
安心してできるトイレの習慣化
便秘が悪化しないように、便意を感じたらすぐにトイレに行く習慣をつけることが重要です。便意を我慢していると、便が硬くなり、排便が難しくなってしまうことがあります。特に、トイレの練習を始めたばかりの子どもにとっては、急かさずにゆっくりとトイレの習慣を身につけさせることが大切です。無理に急がせることなく、安心してトイレに行ける環境を整えることが、便秘予防につながります。 子どもの便秘は、生活習慣の改善を通じて予防・改善できます。無理なく取り組みながら、子どもが快適に過ごせるようサポートしてあげましょう。
よくある質問
便秘はどうしておこるのですか?
便秘がおこる原因は様々ですが、ほとんどの場合は、特にこれといった原因疾患の無い「機能性便秘」と呼ばれるものです。食生活などの生活習慣や、ストレスなどの心因的な要素が関係していることもあります。しかし、中には腸の異常、代謝の異常、内分泌の異常など、何か先天的な障害や、基礎疾患があって便秘になっている可能性もあります。
通常の慢性便秘の治療を行っても効果がなかなか得られないようなケースでは、基礎疾患や先天的な異常がないか、詳細な検査をする必要があります。
成長の段階で便秘になりやすい時期などはありますか?
母乳から粉ミルクなどに変えた時、離乳食を開始した時、トイレの練習を始めた時、入園や入学の時期など、生活に変化が起こった時に便秘が起こりやすいということはあります。
子ども時代の便秘は大人になっても治らないのでしょうか?
5歳以上になって便秘症がある子どもの場合、4人に1人程度は成人になっても便秘症があるという報告があります。
基礎疾患の無い機能性便秘の治療はどのようになりますか?
基本的にはトイレの練習、生活習慣の改善とともに、薬物療法を行います。使用する薬は内服薬、坐薬、浣腸などです。慢性便秘症の場合、治療は即効的なものではなく、時間をかけてしっかり治すものだとお考えください。
使用する薬剤は、
内服薬として、酸化マグネシウム、モビコール、マルツエキス(便を柔らかくする)、ラキソベロン、プルゼニド(下剤)などがあります。
また、坐薬としてはテレミンソフト、新レシカルボンなど、浣腸としてはグリセリン浣腸液などを使用します。
便秘かどうかは、どうやって判断すればよいですか?
便が何日も出ない、排便時に痛がる、便が硬くて大きい、排便後に少量の便が下着につくなどのサインがある場合は、便秘の可能性があります。また、毎日排便があっても、本人が「出しきれていない」と感じている場合は注意が必要です。気になる症状があれば、早めにご相談ください。
便秘の治療中に気をつけることはありますか?
治療中は、急に薬を中止せず、医師の指導に従って継続することが大切です。また、排便の習慣づけや生活リズムの見直しも同時に進めていくことで、より効果的な改善が期待できます。お子さんの年齢や性格に応じたペースで、無理なく進めていくことがポイントです。
受診のタイミングはいつが良いのでしょうか?
2日〜3日排便がないだけで慌てる必要はありませんが、排便時に強くいきむ、痛がる、血が混じる、食欲が落ちているなどの症状がある場合は、早めに小児科を受診しましょう。また、「いつもと違う」と感じたときも、早めの相談が安心です。
 この記事は、
この記事は、
- 日本小児科学会(専門医)
- 日本アレルギー学会(専門医)
- 日本小児アレルギー学会
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 日本小児皮膚科学会
- 母子栄養協会 離乳食アドバイザー
黒岩 玲(あだち小児科 院長)が監修しています。