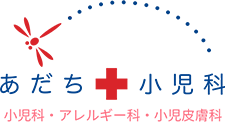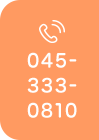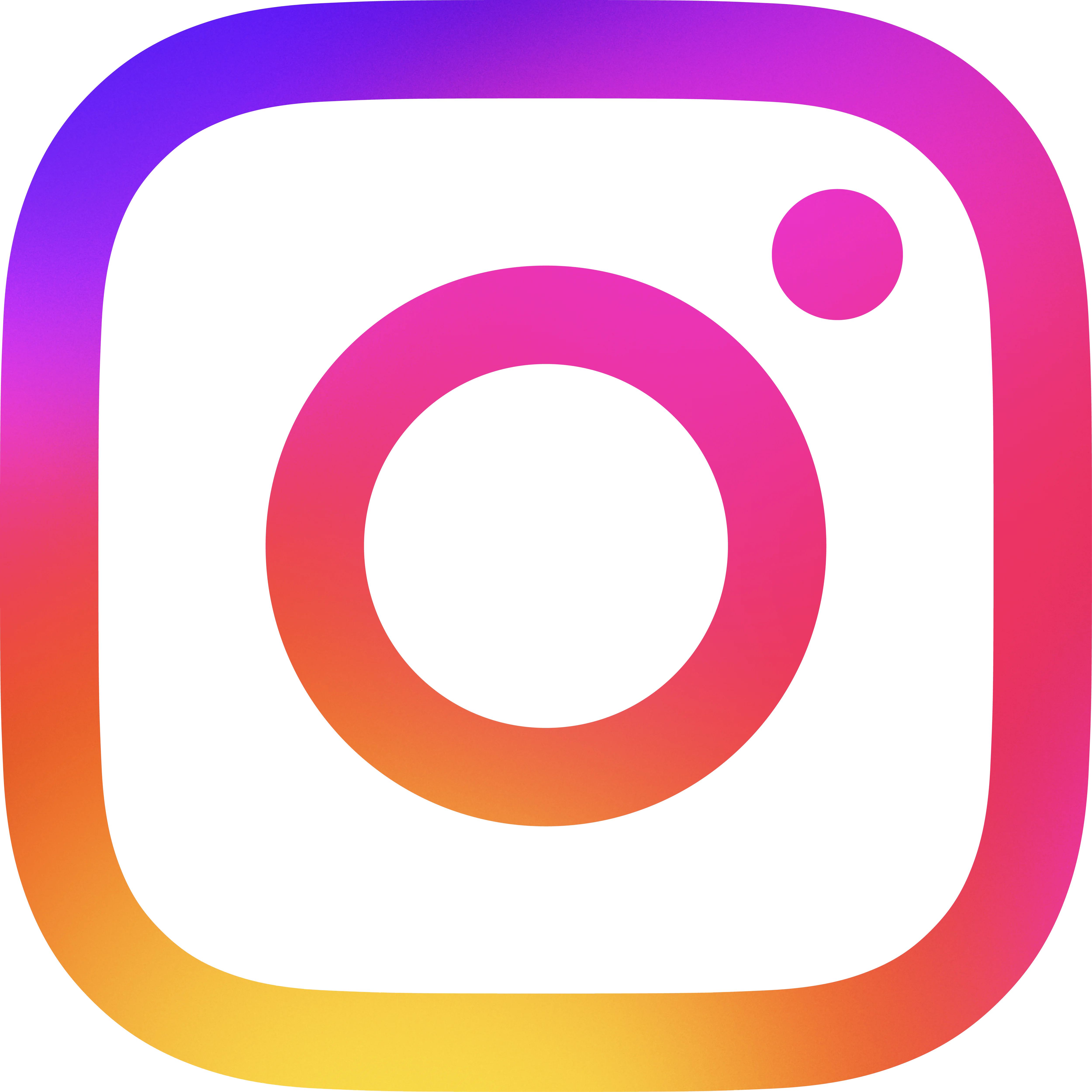当院は発熱外来に対応しております
【発熱者】専用待合・診察室あり
- 37.5度以上の熱が24時間以内にある方は発熱外来をご予約ください。
- 予約された時間にご来院ください。
- ご来院前のWEB問診のご協力をお願いしております。
一般診察の中でWEB問診に記入していただきます。 - 発熱者は専用待合で待機していただき、専用の診察室で診察を行います。
一般診察と導線を分けておりますので、ご安心ください。 - 発熱者の方も一般診察と同じ時間帯で並行して行っております。
- 熱型表を添付するので、お熱の方はダウンロード可能、記入してご来院ください。
子どもの発熱について
 人間の体温は一定ではなく、一日のうちに1℃程度の変動があります。その上で日本人の平均体温は、およそ36.5~37.2℃程度の間とされています。乳幼児の場合、この平均値より少し高い傾向があり、子どもの発熱は一般的に腋の下で測ったときに「37.5℃以上」とされています。発熱を受診の目安ですが熱が高いから重症というわけではありません。全体的な症状を見て判断しましょう。
人間の体温は一定ではなく、一日のうちに1℃程度の変動があります。その上で日本人の平均体温は、およそ36.5~37.2℃程度の間とされています。乳幼児の場合、この平均値より少し高い傾向があり、子どもの発熱は一般的に腋の下で測ったときに「37.5℃以上」とされています。発熱を受診の目安ですが熱が高いから重症というわけではありません。全体的な症状を見て判断しましょう。発熱の原因
発熱する原因としては、ウイルスや細菌による感染症、自己免疫性疾患などの内因性疾患や薬剤によるもの、環境的な問題から発熱する外因性のものなどが考えられます。
そのうち、子どもの発熱として一番多いのは感染性のものです。体内に外敵が侵入してくると、人の身体ではそれに対抗しようとして、リンパ球が活躍します。リンパ球は温度が高いところで活性化するため、外敵と戦うために発熱する仕組みになっているのです。そのため、感染性の発熱の場合は、高熱だからといって無理に薬で下げるようことは必要ありません。感染症による発熱の場合、発熱の仕組みによってストップがかかるため、脳に悪影響が出るとされる41℃を超える発熱はまずありません。
一方、内因性の発熱は、川崎病や膠原病といった自己免疫に関わる疾患で炎症を起こして発熱していることが多く、また薬剤の副作用で熱が出る場合もあります。
外因性の発熱の代表は熱中症です。熱中症の場合、発熱にストップがかかる仕組みが働きにくいため、41℃のリミットを簡単に超える発熱を起こしてしまうことがありますので、この場合は急いで解熱することが大切です。
受診が必要な発熱
子どもが発熱しているときは、全体の症状を見て、急いで受診するべき発熱か、経過を見るだけでよいのかを判断する必要があります。判断は難しいかもしれませんが、以下のような症状がある場合、急いで受診する必要があると判断して良いでしょう。
- 顔色が青ざめている
- 苦しそうに呼吸している
- 大きく息をしている
- ぐったりしていて呼びかけに反応しない
- 朦朧としている
- 何度も嘔吐する
- 頭痛を訴える
- 痙攣がある
- ふだんあまり泣かないのに激しく泣く
- 水分がとれない
- 食事ができない
といった症状の他、生後3か月未満の乳児が38℃以上熱を出した場合や、それ以外でも3日以上熱が続く場合などには、受診をしてください。
熱が上がったり下がったりを繰り返す場合
子どもの体温は、一日の中でもリズムを持って変動しています。特に、朝は体温が最も低く、日中に活動することで徐々に上昇し、夕方にピークを迎えるのが一般的なパターンです。これは、健康な状態でも見られる自然な生理現象です。 たとえば、朝と夕方にそれぞれ体温を測ると、夕方のほうが高い数値になることが多いでしょう。病気による発熱時もこのリズムは影響しており、「朝は少し下がっていたのに、夕方また熱が上がった」というケースは決して珍しくありません。これを知っておくと、必要以上に心配せずにすみます。
ホルモンの働き世より体温の変動
体内では、炎症を抑えるために副腎皮質ホルモン(コルチゾール)が分泌されています。このホルモンは朝から昼にかけて分泌量が多く、体温を安定させる作用を持っています。しかし、午後以降になるとその分泌量が減っていくため、体温が再び上昇しやすくなるのです。 この仕組みを理解しておくと、発熱が夕方に強まる現象も自然なものだと受け止めやすくなります。
子どもや赤ちゃんは体温調節が未熟です
子ども、とりわけ乳幼児は、大人に比べて体温調節の機能がまだ未熟です。そのため、周囲の温度や衣類の厚さなど、環境の影響を受けやすい特徴があります。 たとえば、部屋が暖かすぎたり、厚着をさせすぎたりすると、それだけで体温が上昇してしまうことがあります。また、食事をした後、外で遊んだ後、お風呂に入った後なども、一時的に体温が上がるのはごく自然な反応です。
赤ちゃんの免疫機能はまだ発展途上
赤ちゃんや幼い子どもは、免疫機能も発達の途上にあるため、発熱パターンにも独特の特徴があります。 大人と比べると、熱の上がり下がりが激しく、発熱後すぐに下がったかと思えばまた上がる、といった不安定な経過をたどることも少なくありません。 こうした体温変動は、体が病原体と戦いながら学び、免疫力を高めていくための大切なプロセスです。焦らず、こまめに様子を見守ることが大切です。
対処法
水分補給について
もともと、子どもは身体に含んでいる水分が多めな上、体表面積が体重と比べて大きくなっています。そのため子どもが発熱した場合、水分の放散量が成人より多く、脱水になりやすいことが分かっています。
熱がある時はこまめに水分を補給して、脱水に陥らないようにする必要があります。授乳中の乳児の場合は、母乳やミルクなどでこまめに補給し、離乳後の子どもの場合は経口補水液や麦茶、白湯など、お腹に触らない優しい飲み物で、子どもが飲めるものならなんでも与えて給水するようにしましょう。
もし吐き下していたり、不機嫌になっていたりして飲めないような場合は、すぐにお近くの小児科を受診してください。
母乳や人工乳の与え方
母乳も人工乳も普段通りに飲ませてあげてください。特に人工乳の場合、薄めずに飲ませましょう。以前と異なり、近年では発熱の際でも人工乳も薄めずに飲ませることが推奨されています。またお乳だけで水分不足が心配でしたら、経口補水液なども与えてください。
温度調整と冷やし方
発熱の初期には、悪寒がして震えを起こすことがあります。その場合、布団や毛布などでしっかりと保温する必要があります。しかし、震えが落ち着いて、手足や顔に赤みをとりもどしてきたら、熱が籠もらないように分厚くかけていた布団などを少し薄めに換えます。
やがて汗をかいてくると、熱が落ち着いてきます。汗によって身体を冷やさないよう、濡れた衣類を取り替え、身体をよく拭いてあげます。熱の状態によっては、首や脇の下、太股の付け根あたりを、保冷剤や貼るタイプの冷感剤などで冷やすことも効果的です。両脇を冷やす際は、バンダナまたはストッキングに入れた保冷剤を脇に挟み、たすき掛けをして結ぶ方法もあります。ただし、無理に冷やす必要はありません。
解熱剤の使い方

【38.5℃以上の発熱があり、なおかつ身体がしんどいとき】が解熱剤使用の基準となります。
体温計の数字で解熱剤の使用を判断するのではなく、
熱があるときは、まず腋下(わきの下)・首・鼠径部(足の付け根)を保冷剤等を使って冷やします。
冷やしても
- 機嫌がとても悪く手がつけられない
- ぐったりしていて水分摂取ができない
- 熱にうなされて寝られない
等の時に解熱剤を使います。
たとえば・・・
寝ているときにこっそり体温を計ったら39℃あった!
こんな時は解熱剤を使う必要はありません。そのまま寝かせてあげましょう。こっそり冷やしてあげてください。
解熱剤を使用しても効果が切れれば再び体温は上昇します。
体温のUP DOWNは身体に負担がかかります。
処方されたお薬を内服し、身体を休め、上手に解熱剤を使用していきましょう。
発熱している際の食事
感染症で発熱している場合、食欲も落ちていることが多く、まともに食事ができないケースがあります。そんな時は、まず水分補給を中心に考え、症状のきつい時に無理に食べさせようとする必要はありません。
ただし、乳幼児の場合、まだ肝臓の機能などが未成熟で、体内にしっかりとエネルギーを蓄えられないことがあります。そのため、食事が定期的に摂れていない場合、低血糖を起こしてしまうこともあります。様子を見て、水分がしっかりととれていて、お腹が空いてくるようなら、まずは具を柔らかく煮込んだスープやみそ汁などの流動食を少しずつ食べさせてあげると良いでしょう。
アレルギー体質の子どもの場合、熱のある時や感染症を起こしているときは、免疫機能が敏感になって、普段反応しない食品でもアレルギーを起こしてしまうこともありますので、食材には注意してください。
夜間や休日の場合
対処法を参考にケアをして様子をみてください。ぐったりする様子や、水分が取れないなど、心配な点がある場合は#7119にお掛けになり様子をご相談いただくか、救急病院を受診ください。
救急時の連絡先
| 救急相談センター | #7119 または 045-232-7119(24時間) |
|---|---|
| 保土ヶ谷区休日診療所 | 045-335-5975(日曜祝祭日年末年始10:00~16:00) |
| 横浜市夜間救急センター | 045-212-3535(20:00~24:00) |
| 横浜市民病院 | 045-316-4580 |
※かかりつけ医にご登録の方は専用電話をご利用下さい。
よくある質問
発熱したらすぐに受診した方がよいですか?
熱の高さは受診の一つの目安にはなります。しかし、熱が高いからといって必ずしも症状が重いというわけではなく、特に感染症などの場合、治すために熱が出ているような部分もあります。発熱という症状一つではなく、全身の具合を見て、半日以上発熱が続くようであれば受診を検討してください。明らかに普段と異なる症状があれば受診するようにしましょう。
発熱したら、解熱剤を服用させますか?
感染症などの場合、病原体を退治するために熱を出す身体の仕組みがあります。必要な時に出ている熱をむりやり下げてしまえば、かえって治りが遅くなってしまうこともあります。
しかし、ぐったりして水分補給ができていないといった状態は、脱水症状を起こす危険性もあります。受診するかと同様、全身の症状を良く見た上で、給水ができていない、眠れていないといった場合には解熱剤を使用することも考えます。
解熱剤を服用した場合、どれくらいで効きますか?
小児科では安全性を考えて、子どもの解熱剤には、副作用が少ないアセトアミノフェンを主成分とする解熱剤を使います。この場合、服用後30分程度で効き始め、3~4時間後には最大の効果を発揮します。その後だんだんと効き目が薄れていきますが、平均4~6時間程度は効果を得られます。服用して少し効き始めたぐらいから給水を心がけると、ゆっくり睡眠がとれるようになります。
消化のよい食事はどのようなものですか?
暖かく柔らかいものは一般的にお腹に優しく消化に良いと考えられます。炭水化物でれば、おかゆやよく煮たうどんなど、穀類や野菜であればじゃがいもや柔らかく煮た豆類、豆腐など、たんぱく質では半熟卵、タイやヒラメなどの白身魚の焼き物や煮物、動物性たんぱく質では脂身の少ない鶏肉の胸肉やささ身、果物ではバナナやリンゴ(とくにすりおろしたもの)などはお勧めです。
幼児の発熱は何度からが危険でしょうか?
お子さまの体温が37.5℃以上に達し、さらに次のような様子が見られる場合には、早めに小児科を受診されることをおすすめします。たとえば、普段よりも元気がなくぐったりしている、ぐずる時間が長く機嫌が悪い、母乳やミルク、食事の摂取が明らかに減っている、泣き声が弱々しかったり、普段と違う声になっている、といったサインです。これらは体調悪化の兆候と考えられる為、放置すると症状が進行する可能性もあり注意が必要です。不安を感じたときには、自己判断せず、早めに医師へ相談してください。
発熱があるときにしてはいけない事はありますか?
無理に体温を下げようとすることは避けてください。発熱は体がウイルスや細菌と戦っているサインであり、急激に熱を下げると免疫機能が十分に働かず、かえって病状が悪化してしまうリスクがあります。 また、発熱中の過度な運動は体力を大きく消耗させるため控えてください。さらに、飲酒やカフェインを含む飲料の摂取も、体調を崩す原因となるため避けるべきです。特にカフェインは利尿作用による脱水を引き起こす可能性があります。 加えて、市販薬などを自己判断で使用することも危険です。適切な診断と処方に基づかない薬の使用は、副作用を招いたり症状を悪化させることがあります。 お子さまの発熱時には、安静にし、十分な水分補給を心がけながら心配な点がある場合には、早めに小児科へご相談ください。
発熱にアイスノンは効果的でしょうか?
発熱したお子さまに氷枕やアイスノン、冷却シートなどを使って額を冷やすことはよく行われますが、額を冷やすとひんやりとした感覚があり、一時的に気分が楽になったように感じるかもしれません。ただ、これらの方法はあくまで「心地よさ」を得るためのものであり、直接的に体温を下げる効果は期待できません。 また、冷却によって過剰に体を冷やしすぎてしまうと、かえって体力を奪う原因になることもありますので注意が必要です。発熱時には、無理に熱を下げようとするのではなく、体が自然にウイルスや細菌と戦うのを助けるため、安静にし、水分補給をこまめに行いながら見守ることが大切です。 冷却グッズを使う場合も、あくまでお子さまが「気持ち良さそうにしているか」を目安に、無理のない範囲で使用しましょう。
熱があるとき、手足が冷たくなっているのですが?
赤ちゃんが38度前後の熱を出しているにもかかわらず、手足が冷たく感じられる場合、まだ体温が十分に上昇していない途中のサインであることが多いです。発熱の初期段階では、体が中心部の温度を上げようとして血流を内部に集中させるため、末端である手足は一時的に冷たくなることがあります。 このような場合には、手足を優しく温めてあげることが大切です。体全体が温まり、体温がしっかり上がった後は、赤ちゃんが過剰に熱をこもらせないよう、薄手の服に着替えさせたり、必要に応じて冷却を工夫するなど、こまめに服装や環境を調整してあげましょう。 また、発熱時には体内の水分が失われやすくなるため、こまめな水分補給も忘れずに行ってください。母乳やミルクをいつもより意識して与えたり、必要に応じて水や経口補水液を取り入れると良いでしょう。
熱が上がりきったサインはありますか?
お子さまの発熱がピークに達したかどうかを判断する目安として、手足がしっかりと温かくなっていることが一つのポイントです。発熱の初期には手足が冷たくなることがありますが、体温が十分に上がると末端の血流も改善し、手足までぽかぽかと温かくなります。さらに、顔が赤くほてったような状態になり、体の表面温度も高く感じられるでしょう。また、体温の上昇に伴い、汗をかき始めることもよく見られる現象です。これは、体が過剰な熱を発散しようとする自然な反応です。 このような状態になったら、無理に冷やす必要はありませんが、熱がこもりすぎないように薄着にしたり、室温を調整するなど、環境を整えてあげることが大切です。お子さまの様子をよく観察しながら、必要に応じて水分補給も心がけ、体力を消耗しないように注意してください。
熱を出す予兆などはありますか?
赤ちゃんが発熱する前には、いくつかのわかりやすい兆候が現れることがあります。たとえば、普段より機嫌が悪くなったり、ぐずる時間が長くなったりすることが挙げられます。また、元気がなく、活発さが見られない場合や、顔が赤く火照ったようになることも一つのサインです。 他にも、いつもより長時間眠る、手足がひんやりと冷たく感じられる、鼻水や咳といった風邪のような症状が出る、食欲が落ちてミルクや母乳の飲みが悪くなる、といった変化も注意すべきポイントです。 特に注意が必要なのは、生後3か月未満の赤ちゃんの場合です。この時期の赤ちゃんは免疫力がまだ十分に備わっていないため、少しの体調変化でも重症化するリスクがあります。また、普段とは明らかに違う様子が見られる場合も、迷わず医療機関に相談することが大切です。
 この記事は、
この記事は、
- 日本小児科学会(専門医)
- 日本アレルギー学会(専門医)
- 日本小児アレルギー学会
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 日本小児皮膚科学会
- 母子栄養協会 離乳食アドバイザー
黒岩 玲(あだち小児科 院長)が監修しています。